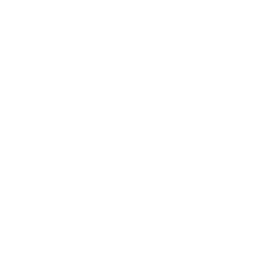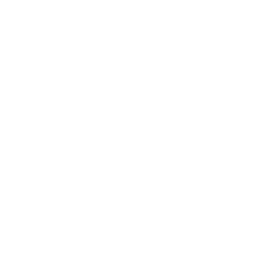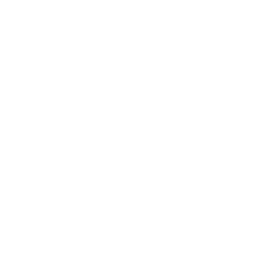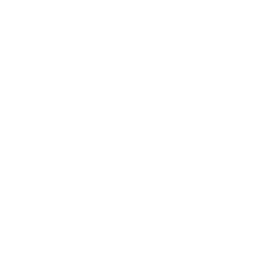「うちのAI」*導入担当者向け

「うちのAI」*は、誰でも簡単に使いこなせる最新型のAIチャットボットサービスです。特別なIT技術に関する知識やプログラミング技術は、必ずしも必要でありません。
「うちのAI」*の導入が期待通りの成果を上げ、御社の事業にとってプラスになるかどうかは、導入前の準備と導入後の運用にかかっています。
現在導入前には、現在抱えている状況や課題を明確にし、それらが解決できた時どんな成果や効果があるのかなるべく具体的に書き出してみてください。こうすることで、「うちのAI」*に任せたい役割が明確になり、学習させるべき情報・データが具体的になり、学習データの収集がスムーズに進みます。更には、運用の仕方やプロンプトでの指示も具体的になり、回答精度の確認も楽しくなります。ここまで来ると、期待した成果が得られる確率が非常に高くなります。
導入後は、とにかく導入した「うちのAI」*を使って欲しいターゲットユーザーに、しっかり告知し御社が「うちのAI」*を導入した事を十分に認知して貰ってください。このステップが運用成果を上げる為の第一ステップで最重要ポイントです。運用をスタートしたら、担当者を決めて定期的に会話履歴を確認し、回答精度のチェック及び修正学習を実施してください。月末には、会話履歴のレポート作成がされますので、担当部署又はチームでその分析を行ってください。*会話履歴応答数が100件以上の場合のみレポートが作成されます。応答件数が少ない場合は、十分に活用されていない事が浮き彫りになってますので、告知活動を強化してください。想定しているユーザーに、なぜ活用しないのかなどアンケートし、要因を突き止めることが解決策となります。
「存在を知らなかった」という回答が多ければ、更なる告知活動が必要で、「使い方が分からない」という回答が多ければ、使い方の講習や簡単な案内資料を作成し、活用が根付くまで丁寧に案内していきましょう。使い方を案内した後、そのユーザーが実際に使えるようになったか確認してあげるサポートも有効となります。「うちのAI」*がユーザーにとって何でも話し合える友人・家族のような存在になるほど、活用されれば自ずと導入成果が上がっている筈です。
「うちのAI」*が修正学習により回答精度を上げれば上げるほど、御社に対する信頼度が上がり、顧客満足度がアップし、さらに使用頻度が上がるという好循環が生まれます。結果、御社とターゲットユーザーとの絆が固くなっていき、ビジネスへの好影響が期待できます。
導入をして頂く限りは、導入コストの何倍も成果を出して頂きたいと本気で考えています。
とにかく導入目的と「うちのAI」*の役割を明確にすること、そして導入した事を知ってもらう事、活用して貰う事が最重要だと言えます。
ある企業の仮想事例
例えば、ある企業で下記のような状況と課題があったとし、経営者がスタッフ採用を検討していたとします。
<状況・課題>
実店舗の来客数が多く、接客スタッフが不足している。混雑した時は、行列ができてしまい、長時間待機しているお客様がいる。この現状を解決する為に、スタッフを補充したいが、中々採用できていない。取り扱い商品が多く、研修もする必要がある。営業終了後、新製品の研修もする必要があり、残業時間が増えてしまい教えるスタッフにもストレスが溜まってしまう。インバウンド客も増えているので、できれば英語を話せる人を採用したい。
<「うちのAI」*を知らない場合のストーリー>
商品を説明できる接客スタッフがあと3人いれば、レジ対応にベテランスタッフを回すことで、売上げアップが期待できる。
月給30万円×3人=90万
売上は上がるけど利益率は下がってしまうな、予算的には2人の採用かな
2人を採用するのに1ケ月を要して、研修を受けてもらい、戦力になり始めた頃に諸事情で1人が退職することになると、また採用からのスタートになり課題解決が進みません。
<「うちのAI」*を知っている場合の解決ストーリー>
「うちのAI」*は、接客スタッフとして人の代わりに商品説明してくれるのであれば、人は会計処理や発送業務に集中できたり、製品の陳列の改善や新商品開発に時間を使うことができる。
しかも、QRコード化し必要な所に配置できるなら商品コーナーごとに配置したいな。入口にもアバターを設置して、お勧め商品を案内して貰いたいな。
よし!資料請求して見積もりを取ってみよう!
「えぇっ!何!? マルチ言語対応で店内のどこでも配置できる!製品情報を即マスター!?自主学習もするの!?それで、このコスト!?専門知識がなくても使えるとは、凄いな!正にうちに必要なスタッフだな。」
「うちのAI」*には、製品説明を任せて接客スタッフの代わりをして欲しいから学習させるデータは、製品のチラシ、説明書とHPの情報だな。よし、フォルダにまとめておこう。
そういえばHPに【「うちのAI」*導入の成功のコツ】ってあったな、導入するなら無駄にしたくないので、従ってみよう。
<導入後の成果>
「うちのAI」*の導入について告知したら、お客様に興味を持って頂きどんどん使って頂いている。
店内に20か所に配置したので、問い合わせの度にスタッフが走り回る必要がなくなった。
お客様も待機する必要がなく、「うちのAI」*が即答してくれるので顧客満足度がアップし、口コミで来店数が増えたが、人がする業務量は削減されており、生産性が上がっているのが実感できている。営業利益も向上している。
インバウンド客にもスムーズに対応できており、期待以上の導入効果があったと思っている。
そして、「うちのAI」*のコスパが凄すぎるとびっくりしている。
店内だけで20か所に配置し、チラシや名刺にもQRコードを印刷し、営業時間外も接客してくれていると考えると、本当にこんな低予算で良いのかと思ってしまうが大変感謝している。導入して大正解だったと実感している。できれば競合他社には使って欲しくないと思います。
導入目的と「うちのAI」*の役割の事例
事例1
| 課題・状況 | 実店舗への来客が多く、接客が間に合っていない。長蛇の列ができ、お客もスタッフもストレスをためている。 |
| 導入目的及び期待する成果 | 接客スタッフの増員による行列の解消と顧客満足度のアップ |
| 「うちのAI」*の役割 | 接客スタッフの代替 |
| 導入タイプ | 「うちのAI Avatar」 アバタータイプを活用することで、リアリティのある接客を演出できます。 |
| 学習データ | 取り扱い商品情報、説明書、注意事項 |
事例2
| 課題・状況 | 展示会に出展しているが、技術スタッフが少なく説明に時間もかかるため、ブースに訪問客が来ても諦めて帰ってしまう。本来は、訪問客と対話して潜在ニーズを聞き取りし、今後の新製品開発に役立てたい。しかし、実際は獲得した名刺の裏にメモ書き程度しか情報収集できていない。 |
| 導入目的及び期待する成果 | 技術スタッフの増員による対話と機会損失の防止。正確な情報収集によるニーズ調査。 |
| 「うちのAI」*の役割 | 対話能力に優れた技術スタッフと速記サポートの代替とレポート作成 |
| 導入タイプ | 「うちのAI Avatar」 アバタータイプを活用することで、リアリティのある接客を演出できます。 |
| 学習データ | 取り扱い製品やサービスの技術情報、専門知識 |
事例3
| 課題・状況 | HP経由の問い合わせが多く、スタッフがその対応で忙殺されているので、業務削減したい。 |
| 導入目的及び期待する成果 | WEB担当スタッフ採用による問い合わせ対応(営業時間外、土日祝日の対応もして欲しい)人が担当する業務量の削減 |
| 「うちのAI」*の役割 | WEB対応スタッフの代替 |
| 導入タイプ | 「うちのAI Chat」又は「うちのAI Avatar」 接客の臨場感を演出したい場合は、Avatarタイプがお勧めです。 |
| 学習データ | HP上(URL)に掲載されている取り扱い製品やサービスの情報 |
「うちのAI」*の活用方向:「社内向け」それとも「社外向け」?
社内向けに活用するのか、社外向けに活用するのか決める。両方で活用したい場合は、社内向け情報の漏洩を防ぐため、社内向け用と社外向け用とそれぞれ1ユニットずつ「うちのAI」*を導入する必要があります。
登録学習させる情報が変わってきますので、取り扱い及び管理にご注意ください。
<社内向け>
社内で共有することで課題解決に貢献するであろう情報が学習対象になります。
課題解決に関連する作業マニュアル、ノウハウ、規則、ルール、技術情報、過去の関連レポート、報告書、品質管理基準のテキストデータ(PDF、word,テキスト、Excelなど)。
<社外向け>
課題解決に関連した情報で、お客様向けに一般公開されているデータ。自社HPのURL、製品やサービスンび関する情報、説明書、製品マニュアル、営業資料などが学習対象になります。
導入チームを作り役割分担する
導入担当者とチームを決め、役割分担を決める。1人が複数の役割を担当する場合でも、それぞれの役割を認識しておくことで「うちのAI」*導入の成果が出やすくなります。
想定される役割
導入窓口となる担当者
役割:見積もりを取り導入検討し、導入する場合は会社決裁を取ることです。支払決済を経理部にリクエストをします。
運用管理者
役割:学習データの登録と管理。プロンプト指示の調整
「うちのAI」*に登録する学習データを準備する人
役割:運用管理者と連携し、登録用の学習データを収集・保存・管理する
「うちのAI」*の回答をチェックする人
役割:ユーザー目線でテスト使用したり、会話履歴を確認し、回答精度を分析する。修正するべき点を発見した場合は、修正させ再学習させる。
レポート機能を活用する人
役割:月に1回自動作成されるレポートを分析し、チームや必要な部署に報告や提案をする